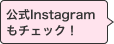内覧会とは?
実際にマイホームの購入を進めていると、「内覧」や「内覧会」といった言葉に出会うことがあるでしょう。内覧会とはどのようなイベントであり、住宅購入の流れのなかではどのような位置付けにあたるのでしょうか?
内覧会とは、「建物完成後、購入予定の住宅の引渡し前に、購入者自身の立ち会いのもと行われる建物の確認」のことを指します。特に新築物件の購入時に使われることが多い言葉です。内覧会は、マンションや建売住宅、または注文住宅などの一戸建てといった、購入する住宅の種類によらず、原則として建物完成後、引渡し前に行われます。ただし、必ずしも「内覧会」という形で行われるとは限りません。
一方で、「内覧」「内見」といった言葉は、賃貸や持ち家を問わず、住宅(建物)の中を確認する際によく用いられます。また、住宅の購入を検討している人に向けて建物を公開するイベントを表す際にも使われます。こちらの意味の「内覧」については、以下の記事で詳しく解説しています。
「内覧会」という言葉は、使われるタイミングで若干意味合いが変わってきます。内容としてはそのときどきですが、次の2つを示すことが多くなります。
[ 1 ] 建物完成後、物件引渡し前の建物の最終チェック
「内覧」や「内見」は多くの場合、単純に物件見学を指しますが、内覧会は、売買契約後、建物が完成し、物件引渡し前に行われるものを指します。特に新築で購入した物件が、事前に目にしていたパンフレットや設計図、仕様書の通りに造られているかを分かる範囲で確認します。
この際、完成した建物に汚れや傷といった不具合がないかもチェックします。問題が見つかれば、内覧会でその箇所を指摘します。ここで指摘することで、売主や施工会社は指摘箇所の修理や設備の交換を可能な限り引渡しまでに行います。
[ 2 ] 施工業者や販売業者による、自社宣伝のための見学会
見学会を意味する「内覧会」は、実際にその会社で建てた住宅を、施主である住宅購入(新築)者の了解のもとで一般公開するイベントです。近隣の住宅購入や新築に興味のある人を呼び込み、施主への引渡し前に建物を見学してもらいます。目的は、ハウスメーカーや不動産会社といった施工業者や販売業者が、自社のデザイン性や施工能力を宣伝することです。
本記事では、[ 1 ]の意味で使われる「内覧会」について、その目的やチェックすべきポイント、当日の流れについて詳しく解説していきます。

内覧会が大事な理由
内覧会は、以下の2つの点から、必ず参加しておきたいイベントといえます。
入居前に完成した建物の不具合を指摘できる
内覧会は、引渡し前のタイミングで、完成した住宅を実際に確認できる貴重な機会です。内覧会では、間取りのほか、床、天井、壁の傷・汚れ、各種設備の不具合があれば、売主や施工業者に指摘します。指摘した事項は、可能な範囲で引渡しまでに修繕してもらえるため、購入した物件をよいコンディションで引渡ししてもらえるようになります。もちろん、指摘事項がないに越したことはありませんが、あってもきちんと対応してもらうことで、気持ちよく引渡しを受けられるでしょう。
ちなみに、内覧会で見つかった不具合については、購入者や施主の修繕費負担は原則として発生しません。修繕は引渡しまでに行われることが多いものの、間に合わない場合には、相談のうえ引渡し後に修繕を行うケースもあります。
基本的に新築住宅の場合、建物や設備の不具合は、入居後も一定期間内であれば申告する機会が用意されており、指摘事項は基本的に修繕してもらえることになっています。ただし、フローリングや壁に付いた傷は、入居前からあるものなのか、引越しや生活のなかで購入者が付けてしまったものなのか判断できない場合があるため、これらの傷は、やはり内覧会で指摘しておくことが大切です。引越し作業後にフローリングや壁などの傷を指摘しても、売主や施工業者に無料で修繕してもらえるとは限りません。
なお、給湯器やガスレンジといったガス機器は、入居後開栓手続きをしないと設備の不具合の有無が確認できないので、通常、引渡し後2週間~1か月以内に不具合の確認をすることになっています。ガス機器については、期間内に開栓し、忘れずにチェックシートに記入するようにしましょう。
家具配置を検討できる
内覧会は、完成した建物内にどのように家具や家電を配置するのかを検討する機会でもあります。実際に家の中を見て、実寸を測って家具や家電の収まりを確認しましょう。家具や家電以外のカーテンやカーペットといった内装のプランを考えるのにも役立ちます。

内覧会でチェックすべき項目
引渡しを気持ちよく受けるためには、内覧会でどういった点をチェックすればよいのでしょうか?どのような物件でも必ず見ておくべきポイントと、一戸建て・マンションそれぞれで見るべき項目について、具体的に解説します。
共通して必ず見るべき項目
一戸建てとマンションのどちらの場合でも、以下の項目は必ずチェックしておきましょう。
●パンフレットや設計図面通りに造られているか
実際に完成した建物が、事前に確認していたパンフレットや設計図面の通りになっているかをチェックしましょう。収納スペースの位置や大きさ、天井高や梁の位置、各部の寸法、コンセントや照明の位置については、できる限り寸法を測ってチェックしておきたいポイントです。購入時にオプションを付けた場合には、指定通りのオプションが設置されているかも確認しておきましょう。
●施工精度に問題がないか
床や壁がしっかりと水平・垂直に建てられているか、ドアや窓の建て付けに問題がないかをチェックすることが大切です。床に傾きや浮きはないか、ドアや窓の開閉はスムーズに行えるかを漏れなく確認しましょう。

●設備は正常に動くか
設置された設備がきちんと動くかも、重要なチェック項目といえます。設備チェックの際は、台所や風呂場といった水回りの機器を重点的に確認するほか、インターホンや換気扇などの電気機器も正常に作動することを確かめましょう。ただし、前述の通りガス機器は開栓しないと確認できないため、入居後にチェックを行うことが一般的となっています。
●傷や汚れはないか
床や壁紙、ドア、扉といった箇所に、傷や汚れが付いていないかをチェックしましょう。壁紙の傷や浮き、フローリングや畳の傷は、引越し後になると、いつ付いた傷なのか判別できず、補修が有料になってしまう場合があります。内覧のうちにきちんと指摘できるように、チェックは丁寧に行いましょう。その際、傷や汚れが見つかり修繕を依頼する箇所については、その状態を写真に残したうえで、付箋紙を貼り、場所の記録をしておくとよいでしょう。
一戸建てで見るべき項目
上記のチェック項目に加え、一戸建ての内覧会では、屋外の設備や構造物についても、不具合がないかを確認することが大切です。
●基礎や外壁
建物の外観は、見た目だけでなく、基礎のコンクリートにひび割れのようなものはないか、外壁に仕上げ材の剥がれがないかなども、見える範囲でチェックしましょう。
●外構
「外構」とは、建物の外にある構造物のことで、具体的にはブロック塀やフェンス、駐車場、植栽、玄関部分の外側などが挙げられます。塀やフェンスは揺らしてみてブレがひどくないか、駐車場は仕上がっているか、また植栽については計画された樹木が植えられているかといったところまで確認しましょう。加えて、ガスや水道のメーターが正しい設置場所に設けられているかどうかも大切なポイントです。
また、近隣トラブル防止の観点から、敷地境界線は明確か、明らかに境界からはみ出したものが造られていないかもチェックするように心掛けましょう。

マンションで見るべき項目
マンションは、大きく住戸内の「専有部分」とそれ以外の「共用部分」に分類されますが、マンションの内覧会の際は、基本的に専有部分の不具合のチェックがメインになります。まずはしっかりと専用部分をチェックし、余裕があれば、共用部分の確認を行うとよいでしょう。
共用部分については、不具合のチェックよりもエントランスドアの操作方法や、宅配ボックスの使い方のチェック、駐車場や駐輪場、ゴミステーションの位置の確認などがチェックすべき点として挙げられます。マンションの共用部分の設備については、以下の記事で詳しく解説しています。
内覧会に行く前の準備
ここまで解説してきたように、内覧会は、新築住宅の建物完成後、引渡し前に最終確認を行える貴重な機会です。不具合の発見や採寸を効率的に進めるには、どのような準備をしておくべきなのか確認していきましょう。
持ち物を準備する
内覧会前には以下のものを準備しておくと、当日不具合のチェックをスムーズに進められるうえ、修繕を依頼する際に位置や状態を伝えるのにも便利です。通常、内覧会では売主や施工業者が一通りチェックするための準備をしてくれる場合がほとんどですが、それでも自分でメジャーやカメラなどは用意しておくと確実でしょう。
- パンフレットまたは設計図面
- メジャー
- 水平器
- カメラ
- 懐中電灯
- 付箋紙
- スリッパ
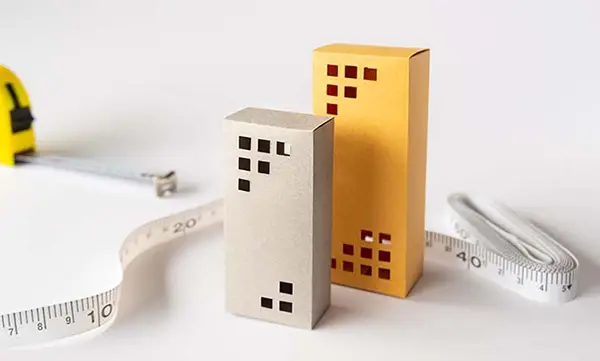
2人以上で参加する
これまでご紹介したように、内覧会ではさまざまな部分の不具合を確認することになります。そのため、1人で家中の全ての箇所をチェックするのは大変なので、できれば2人以上で内覧会に参加し、協力してチェックを進めていくことで、チェック漏れのリスクを抑えられます。
当日のスケジュールを確認する
内覧会当日のスケジュールは、大規模なマンションや複数の一戸建ての場合、業者側から時間を指定されることが一般的です。しかし、不具合のチェックを入念に進めていると、どうしても時間がかかってしまうことも想像されます。時間内でしっかりチェックできるよう、重点的にチェックしたい項目をあらかじめリストアップしておくとよいでしょう。
また、内覧会当日だけでなく、内覧会から引渡しまでのスケジュールも確認しておきましょう。不具合を見つけ、修繕を依頼した場合、修繕に日数を要することが考えられます。修繕の箇所や内容によっては、修繕が終わるのが入居後になってしまうこともあります。一戸建ての場合は、マンションと比べて修繕に時間がかかりやすいため、内覧会を引渡し直前に設定しないように心掛けましょう。

内覧会当日の流れ
不具合のチェックや採寸をじっくりと行うため、内覧会当日は一日のスケジュールに余裕を持っておきたいところです。では、当日はどのような流れで内覧会が進められるのでしょうか?ここでは、新築マンションの内覧会を例に、当日の流れは、以下の通りです。
- 指定された日時に集合
- 内覧会の流れの説明
- 住宅や設備についての説明
- 内覧・検査(チェック)
- 指摘箇所の提出
- 終了後、適宜解散
[ 1 ] 指定された日時に集合
マンションの販売業者に指定された日時に、指定された場所へ集合します。購入した物件で現地集合となることが多いものの、まれに購入物件以外の場所でいったん集合する場合もあります。また、規模が大きいマンションの場合、内覧会は数日に分けて実施されることがあります。この場合は、それぞれの日において集合時間が指定される形になりますが、都合が合わない場合は、早めにいえば日程を調整してもらうこともできます。
[ 2 ] 内覧会の流れの説明
売主や施工業者から、内覧会の進め方について説明が行われます。内覧会が始まる前に、不具合のチェック用の指定用紙を配布されることが一般的です。
[ 3 ] 住宅や設備についての説明
住戸内に設置された設備の使い方について説明が行われることもあります。電気機器や水回りの設備は、動作確認も可能です。ただし、ガス機器については個別に開栓手続きが必要なため、引渡し後に確認することになります。また、特にマンションについては、これに加えて共用部分の使用上のルールについても説明されることがあります。
[ 4 ] 内覧・検査(チェック)
室内の状態をチェックし、不具合がないかを確認します。不具合が見つかった箇所は、チェック用の指定用紙に記入しましょう。また、通常は、指摘箇所に付箋紙やマスキングテープなどを貼っておくのが一般的です。
[ 5 ] 指摘箇所の提出
見つかった不具合(指摘)箇所を、指定用紙に書いて提出します。細かい指摘や分かりにくい部分は口頭で担当者に説明しましょう。また、修繕がきちんと行われたかを後日(引渡し時に)チェックするため、不具合の状態を写真に残しておくことがおすすめです。
[ 6 ] 終了後、適宜解散
不具合のチェックと報告が済んだら、内覧会は終了となります。補修が必要となる場合、しっかりと補修が行われたかどうか、後日引渡し時に再確認することが一般的です。
入居前に内覧会を活用し尽くそう!
「内覧会」を行う目的や必要となる準備、当日の流れについて解説してきました。何度もお伝えしてきたように、内覧会は建物完成後、引渡し前にじっくりと物件を確認できる数少ない機会です。不具合を見つけたら、売主や施工業者に遠慮なく伝え、修繕を依頼しましょう。
購入物件に不具合のない状態で入居できるよう、内覧会をしっかりと活用し、引渡し前の不安をなくしていきましょう!