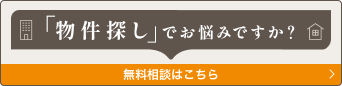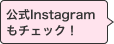共有名義で購入する際の住宅取得資金贈与利用のメリット
共有名義で物件を購入する場合に住宅取得資金贈与の非課税措置を利用するとどんなメリットがあるのでしょうか?
まず、この制度には非課税になる限度枠が決まっています。そこで夫婦2人の共有名義で物件を購入すると、非課税の限度枠を2人それぞれで使えます。つまり、単独名義で物件を購入するよりも非課税限度額が2倍になるというわけです。
援助してもらう資金が増えれば、その分を頭金や諸経費に充てて、住宅ローンなどの借入金を少なく抑えることができます。月々の返済額をセーブすることができるので、家計にゆとりが生まれるというメリットがあります。
ほかに、親から非課税限度枠以上の援助を受けたい場合は、物件を購入する際の名義を親と共有にすることで解決できます。これは、親に贈与税の非課税限度枠いっぱいの資金を援助してもらい、共有名義人でもある親に残りの資金を負担してもらうというイメージです。このように、お得な制度を上手に運用することでより物件が購入しやすくなります。

共有名義で購入する際の住宅取得資金贈与利用の注意点
共有名義で物件を購入すると贈与税の非課税枠が広がる住宅取得資金贈与。この非課税措置を利用する際には以下のような3つの注意点があります。
- 非課税の対象は直系尊属のみ
- 共有持分の配分は負担資金の割合で算出
- 贈与を受けた人がその分の贈与税を申告
それぞれ具体的にどういったことなのか、詳しく解説しましょう。
[ 1 ] 非課税の対象は直系尊属のみ
住宅取得資金贈与の非課税措置の条件には、自分の親や祖父母などの直系尊属からの贈与であることが挙げられます。義理の親や祖父母からの贈与には適用されません。たとえば夫の名義のみで物件を購入するときに、妻の親から贈与を受けたとすると対象外となり課税されてしまいます。妻の親からの贈与はあくまでも妻が受け取らなければ対象とはならないということです。
[ 2 ] 共有持分の配分は負担資金の割合で算出
物件を共有名義で購入する場合、それぞれが所有する物件の割合を明示した共有持分というものを決めなければなりません。その際に、それぞれの持分の割合は実際に負担する資金の割合と同じになるようにしましょう。この場合の資金負担とは、親などからの贈与、自己資金、住宅ローンを含めます。
たとえば、夫と妻が共有名義で物件を購入するとき、それぞれの自己資金や親からの贈与額の合計が同じ金額だったとします。この場合、一見、資金負担を5:5だと考えてしまいがちです。しかし、夫の名義で住宅ローンを組んでいるとすると、ローンを含めて考えた実際の合計負担額の割合は夫の方が高くなります。そのため、持分の割合も合計負担額の割合に合わせて、夫の方を高く設定することが妥当となります。
もしもこの場合に、共有持分の割合を負担額と違った割合で設定してしまうと、一方がもう一方から贈与を受けているとみなされるなど、将来的にトラブルに繋がることがあります。
[ 3 ] 贈与を受けた人がその分の贈与税を申告
住宅取得資金贈与の非課税措置を利用するためには、必ず贈与税の申告を行わなければなりません。これは、贈与税が0円となる場合でも同様です。そして、その申告は、それぞれ贈与を受けた本人が申告する必要があります。共有名義だからといって、どちらか一方がまとめて申告することはできませんのでご注意ください。
さて、このような注意点に気をつけて対応すれば、この制度自体は物件購入にとても有効です。ただし、共有名義を夫婦で利用する場合は、離婚の際に物件売却や残ったローンの支払いなどで揉めることもあります。共有名義を親子で利用する場合は、親が亡くなったときの相続でのトラブルも想定されます。これから購入する場合はこのようなことを踏まえて検討しましょう。