マンション購入ガイド
![]()
マンションを共有名義で購入したらどうなる?
結婚を機に、マンションの購入を検討中です。2人でお金を出し合うので、共有名義になるな…と単純に考えているのですが、注意しなければいけないことはありますか?
たとえば、不動産を共有名義で購入すると、相手の同意なしに売却などをすることはできません。そのほかにも共有名義では注意点がありますので、それらを踏まえた上で検討しましょう。
情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸
目次
マンションの「共有名義」とは?
不動産の購入には、多額の資金が必要となるもの。そこで、1つの不動産を複数の人がお金を出し合って購入する場合がありますが、このとき出資額の割合に応じた持分(もちぶん)を登記することを、「共有名義」(共有登記)といいます。
共有名義でマンションを購入している夫婦や家族などの例はよく聞かれますが、安易に共有名義としてしまうと、後々困ることもあるかもしれません。
ここでは、マンションを共有名義で購入する場合のメリットと注意点について、分かりやすく解説します。

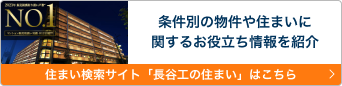
夫婦で共有名義にするメリットと注意点
結婚をしたタイミングでマンションを購入するという方は多いのではないでしょうか。その場合、どちらか一方ではなく夫婦2人でローンを組んだり、一方が頭金を出して他方が住宅ローンを組んだりするなど、支払い方法の選択肢はいくつか挙げられますよね。このように夫婦で共有名義にした場合、どのようなメリットと注意点があるのかご紹介します。
夫婦で共有名義を選ぶメリット
マンションを購入する場合、多くは住宅ローンを利用することになりますが、住宅ローンを2人の名義で組み、夫婦でマンションを共有名義にすると、物件や人的要件を満たした場合、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」をそれぞれの収入に対して受けることができます。
たとえば、夫婦それぞれがローン契約する「ペアローン」、または、夫婦のうち1人が主債務者・もう1人が連帯債務者になる「連帯債務型ローン(フラット35など)」などは、共有名義で住宅ローンを組みたい人向けの仕組みです。
夫婦共有名義のもう1つのメリットは、相続税を節税できること。仮に、夫が亡くなって妻に不動産が相続される場合、単独名義だとその不動産まるごとの評価額が課税対象になりますが、共有名義であれば、夫の持分のみが課税対象になります。
夫婦で共有名義を選ぶ注意点
共有名義にした不動産は、共有者全員の同意なしに売却などをすることはできません。もし、夫婦が将来離婚することになった場合、売却に際して意思疎通が難しくなり、夫婦間の価格の折り合いがつかないなどスムーズな売却ができないといったことも起こり得ます。また、離婚して一方がその住宅に住み続ける場合など、夫婦2人で住宅ローンを組んでいるケースでは、残った住宅ローンの返済なども含めてトラブルになる可能性も考えられます。
事実婚の場合
入籍していない、いわゆる事実婚のカップルの場合でも共有名義にすることは可能です。ただし、互いを連帯保証人とするペアローンを利用することは難しいなど住宅ローンを利用しての共有名義には制約があります。また、事実婚の場合は、一方が頭金を出すなどのケースで共有することが可能ですが、共有名義にした場合、婚姻関係にある夫婦よりも問題が起きやすい傾向はありますので、注意が必要です。
なお、「フラット35」は内縁関係でも共有名義でローンを組むことができるので、事実婚でのマンション購入を考えている場合は検討してみてもよいかもしれません。
マンションを親子・兄弟で共有名義にする場合
夫婦だけではなく、家族同士でも共有名義でマンションを購入することは可能なのでしょうか。こちらもメリットと注意点に分けてご紹介します。
親子・兄弟で共有名義を選ぶメリット
家族同士でマンションを共有名義にする場合、親子で共有名義とする場合と兄弟姉妹で共有名義とすることなどがあります。親子で共有名義にする場合、親に十分な資金がないときでも「親子ペアローン」や「親子リレーローン」を利用して、共有名義とすることができます。これらのローンを利用した場合、親子それぞれが持分に応じて住宅ローン控除を受けることは可能です。
親子ペアローンは、親子が別々に住宅ローンを借り入れするので、それぞれの年収を合算した金額でローンが借りられ、融資を多く利用できる点がポイントになります。ただ、親子がそれぞれ同時に返済していくので、一方が返済できなくなるともう一方の負担が大きくなるという注意点があります。
一方、親子リレーローンは、親の退職後や年齢が銀行等の定める完済年齢に達した後などに子が返済を引き継ぐというものです。購入時点で親が一定の収入はあるものの、高齢であまり長期の住宅ローンが組めない場合やまだ子供の年収が少ない場合などに、親子リレーローンを利用します。
また、親から住宅購入資金の一部を現金で援助してもらい、子がローンを組むといった場合も、共有名義にすることができます。この場合も出資割合に応じた共有持分とすれば、贈与税の対象にはなりません。
なお、現在は、子が住むための住宅を取得する際に親が子にその取得資金として援助する場合には一定額まで贈与税が非課税になる特例(「住宅取得資金贈与の特例」)があります。
親子間で共有名義にする場合は、親が亡くなった後の相続についてもあらかじめ考えておく必要があります。
もし、親の相続財産の相続人が自分だけでなく兄弟などもいる場合、その住宅の共有持分が原因で相続を巡るトラブルが起きてしまうかもしれません。「そのマンションに住み続ける共有者が親の共有持分を、事前の話し合いや遺言などで相続できるようにしておく」など、後の対策を講じておきましょう。
親子・兄弟で共有名義を選ぶ場合の注意点
一方、兄弟姉妹の共有名義でマンションを購入しようという場合は、通常、互いに現金を用意し合うか、一方が頭金を用意し、もう一方が住宅ローンを利用して共有名義にすることになります。理由としては、住宅ローンのペアローンの借り入れが難しいとされているからです。一般的に金融機関はペアローンを貸す際、「そのマンションに一緒に住み続ける」ということを前提としています。ところが、兄弟姉妹の同居となると、将来どちらかが結婚して家を出るなどの場合も考えられ、前提が崩れてしまう懸念があるため、ペアローンが利用しにくくなっているのです。
ただし、金融機関によっては例外もある可能性はありますので、どうしても兄弟姉妹でペアローンを利用したいという場合は一度相談してみるとよいでしょう。
共有名義にする場合、親子でも兄弟姉妹でも、「結婚が決まった」「仕事の都合で転居が必要になった」などの理由から、共有者の誰かがそのマンションを出て新たに住まいを購入したいと思うことがあるかもしれません。そのとき、特に、住宅ローンを利用した共有名義のマンションがあることによって、新たな住まいを購入する足かせになってしまう場合もないとはいえない点も注意が必要かもしれません。また、頭金など現金を出した共有名義の場合でも、その出資した資金の扱いについて、新たな住まいの購入資金としたいので、住み続ける方にその分を返してほしいと要求するなど、揉めることもあり得ます。
共有持分割合に注意
共有名義にする際の共有持分は、共有者の出資割合に合わせたものにすることも重要な注意点のひとつ。もし、出資した以上の持分を持つことになると、本来の出資額を超えた分について贈与税が課されることになります。
たとえば、夫婦2人で、5,000万円のマンションを、妻が頭金500万円と妻名義の住宅ローン1500万円、夫名義で住宅ローンを3,000万円組んで購入するとします。このとき、それぞれのマンションの持ち分を妻1/2、夫1/2としてしまうと、実際の出資割合は妻2/5、夫3/5ですから、マンションの1/10相当を夫が妻に贈与したことになってしまいます。この例では、500万円分を贈与したことになり、
贈与税=(500万円-110万円(基礎控除))×20%-25万円=53万円
を支払うことになってしまいます。
余分な税金はなるべく納めたくないものです。くれぐれも出資割合と共有持分の割合には注意するようにしましょう。
ここまで解説してきたように、マンションといった不動産を共有名義で購入する場合は、夫婦、親子、兄弟姉妹など共有する関係性を冷静に捉えることが重要です。そして将来のライププランを想定しながら、じっくりと検討しましょう。大切な家族やパートナーと協力して、よりよい選択ができるように進めていきたいですね。

情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。不動産コンサルタントとして、物件の選び方から資金のことまで、住宅購入に関するコンサルティングを行なう。